[コラム]モバイルバッテリーが発火したときの正しい処分と安全対策【2025年最新対応】
2025.07.29
モバイルバッテリーが発火したときの正しい処分と安全対策【2025年最新対応】
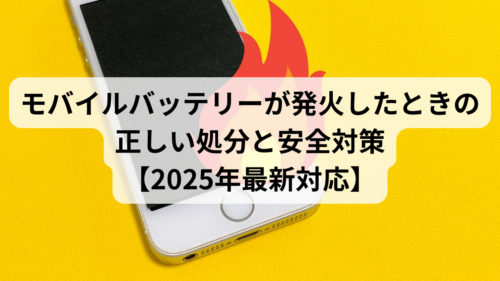
スマートフォンやモバイル機器の普及に伴い、リチウムイオン電池を搭載したモバイルバッテリーは欠かせない存在となりました。しかし、発火事故の増加により、その危険性も注目されています。
特に、発火したバッテリーの処分を誤ると、再発火や火災など重大なトラブルを招くおそれがあります。本記事では、家庭および法人向けに、安全で法令に準拠した処分方法を詳しく解説します。
※地域によって処分方法が異なる場合がありますので、最終的にはお住まいの自治体の案内をご確認ください。
なぜ発火後のバッテリーは危険なのか
- 内部のリチウムイオンセルが露出し、わずかな衝撃で再び発火するリスクがある
- 収集車両やごみ処理施設での火災事例が増加中
- 多くの自治体が「通常ごみ」への混入を禁止している
見た目に火が消えていても、化学反応が継続している可能性があるため、取り扱いには十分な注意が必要です。
発火直後の応急措置
- 自然冷却を優先
バッテリーは火が消えた後も内部が高温です。コンクリートやタイルなどの不燃床に置き、24時間以上は自然に冷ましましょう。 - 金属容器に隔離
冷却後、砂を敷いた金属容器に入れ、蓋を軽く乗せてガスを逃がせる状態にします。 - 端子を絶縁
ショート防止のため、電極部分にはテープでしっかりと絶縁処理を行います。 - 迷ったら消防に相談
状況が不安な場合は、119番で専門の指示を仰いでください。
家庭での処分方法
自治体の清掃事務所へ持ち込む
通常の不燃ごみでは処分できないため、清掃事務所またはごみ減量推進課などへの持ち込みが基本です。
例:東京都大田区
発火のおそれがある場合、以下のいずれかに持ち込むことで無料処理が可能です。
- 大田区ごみ減量推進課(03‑5744‑1628)
- 大森清掃事務所(03‑3774‑3811)
- 蒲田清掃事務所(03‑6459‑8201 / 03‑6451‑9535)
大田区以外の方は、自治体の施設案内を確認してください。
JBRC(小型充電式電池リサイクル協会)を利用する
JBRCは全国に回収協力店を展開していますが、以下のような状態の電池は対象外です。
- 焦げ跡や液漏れがある
- バッテリーが膨張している
- 水濡れが疑われる
対象外の場合は、公式サイトで電話相談のうえ、対応店舗をご確認ください。
メーカーや販売店の回収・リコール対応
製造上の不具合により、リコールの対象となっている場合は無償回収されることがあります。
リコール情報の確認は、消費者庁の公式サイトをご参照ください。
法人・事業者による廃棄時の注意点
業務用バッテリーの処分は「産業廃棄物」として分類され、廃棄物処理法に基づく対応が求められます。
- 分類:廃プラスチック類、金属くず、汚泥など
- 梱包:UN3480/UN3481準拠、混載不可
- 処理:マニフェストの交付・管理義務あり
許可を持つ専門の産廃業者に依頼することが、安全性と法令遵守の面からも必須となります。
よくある質問(FAQ)
Q.火が消えたらすぐに処分していいですか?
内部に熱が残っている場合があるため、少なくとも24時間の冷却が必要です。
Q.不燃ごみに出せますか?
多くの自治体で不可。清掃事務所等への持込みが必要です。
Q.JBRCの回収ボックスに入れても大丈夫ですか?
破損・膨張・液漏れがあるバッテリーは対象外です。事前相談を推奨します。
Q.水で冷やせば安全ですか?
表面が冷えても内部反応が続いている可能性があり、再発火の恐れがあります。
Q.宅配便で返送できますか?
発火バッテリーは航空法等により送付不可。メーカーの専用回収手順に従ってください。
まとめ|再発火を防ぐには「知識」と「行動」が鍵
- 火が消えても油断せず、必ず自然冷却と絶縁を
- 耐火容器での保管・輸送が基本
- 各自治体・専門機関の指示に従って処理
正しい対応を知り、身近な火災リスクを未然に防ぎましょう。
当社では、法人様および個人事業主様を対象に廃棄物の処理を承っております。
個人のお客様につきましては、未使用品の大量廃棄の場合のみ対応可能です。
誠に恐れ入りますが、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
著者紹介

名前: 中林 一樹(なかばやし かずき)
プロフィール
2014年より株式会社アール・イー・ハヤシに入社。以降10年間、産業廃棄物管理のスペシャリストとして従事。
産業廃棄物の処理とリサイクルに関する豊富な経験を持ち、環境保護に対する深い知識と情熱を持っています。
現在も、株式会社アール・イー・ハヤシの管理部門で環境管理責任者として、日々業務に励んでいます。

